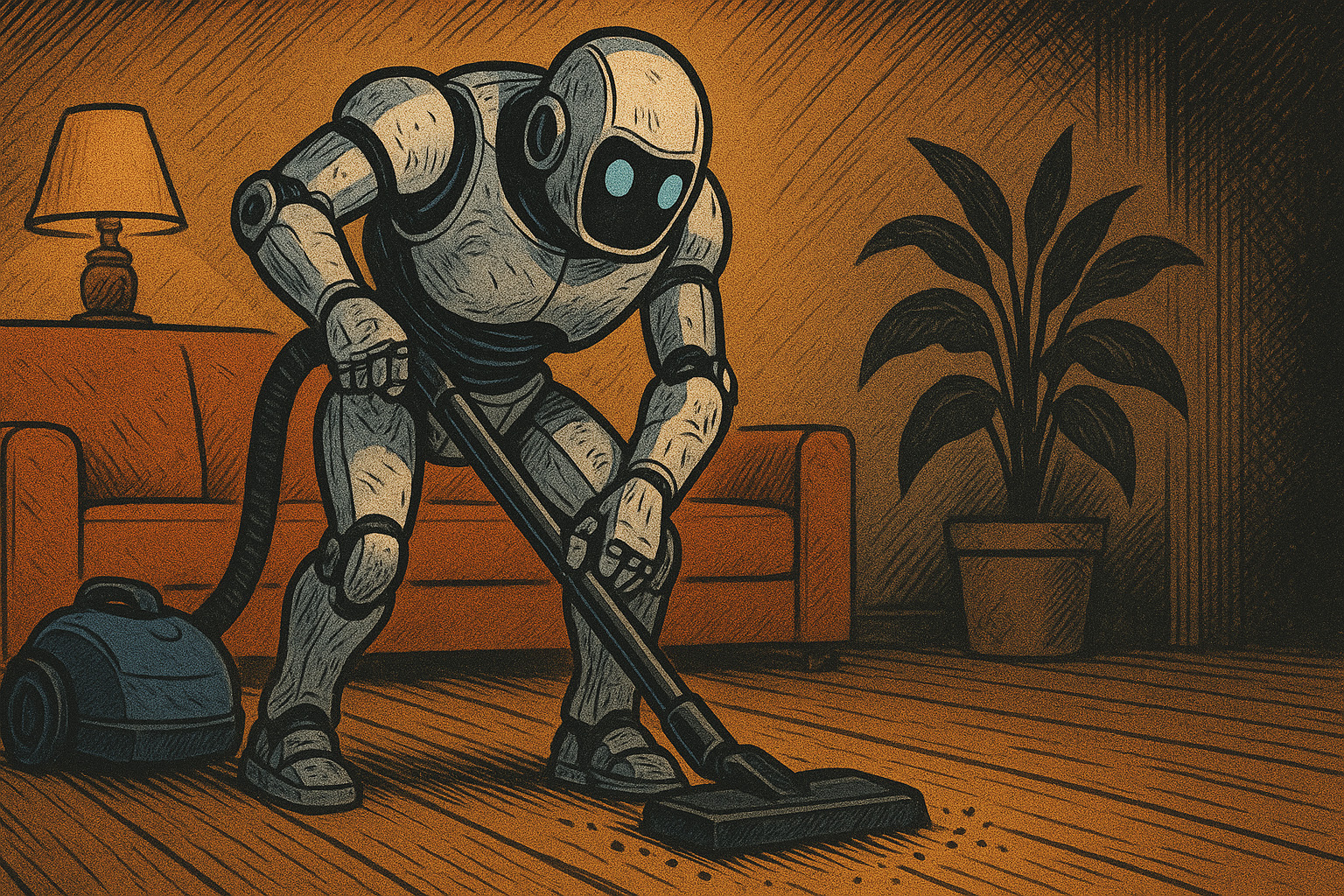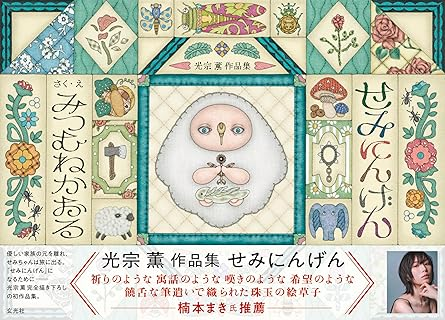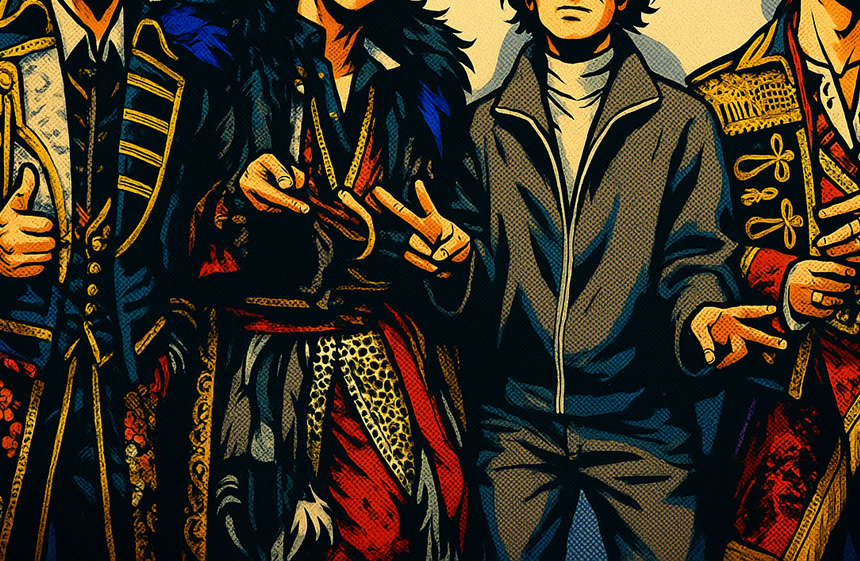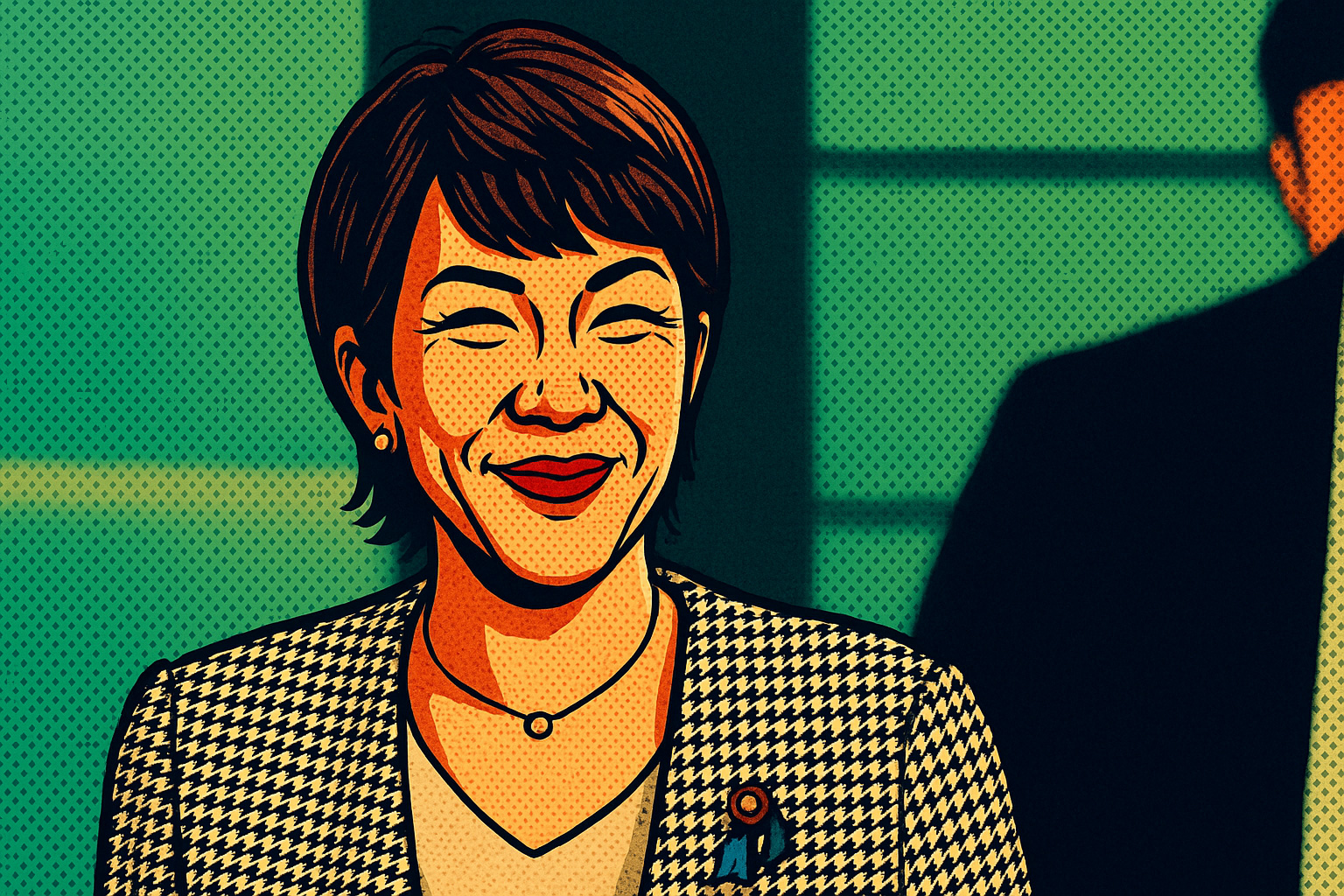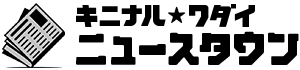近年、人里に出没するクマのニュースが増えています。
クマによる被害が報道されるたびに駆除を求める声が上がる一方で、クマの駆除に反対する意見も多く見られます。
ヒグマ駆除は正義か残酷か?全国から200件超の意見『かわいそう』vs『安全確保を』(Yahoo!ニュース)
実は、クマの駆除には生態系への影響や法律上の制約など、さまざまな課題があります。
危険な野生のクマを駆除しない理由と、海外で取り組まれているクマ対策「共存・共生」について解説します。
なぜ?危険な野生のクマを駆除しない理由
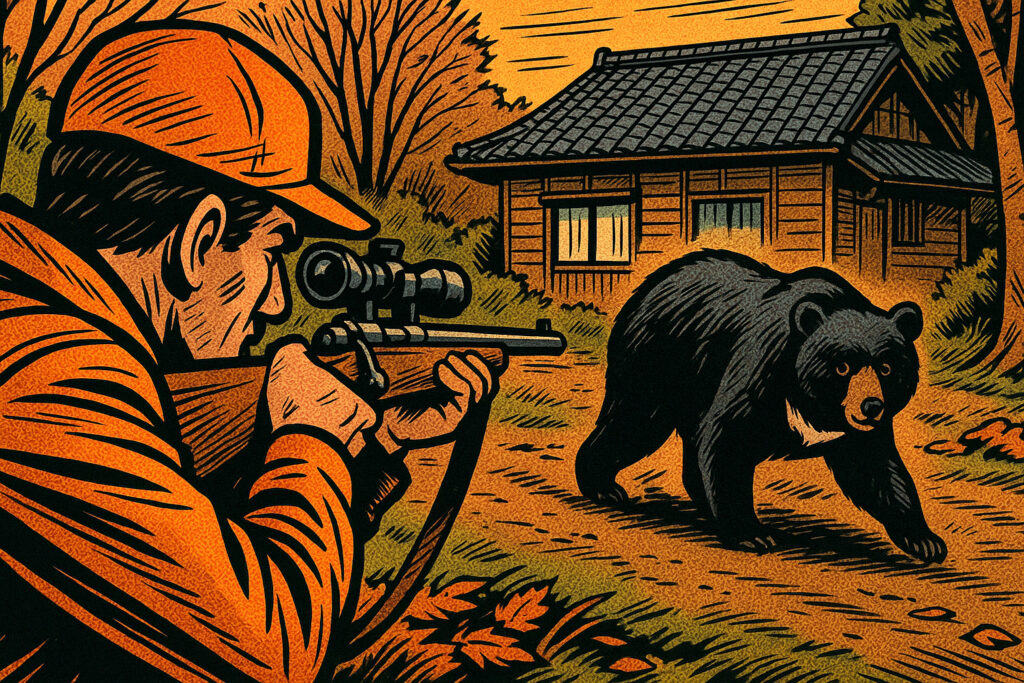
危険だとわかっていてもクマをすぐに駆除しないのは、それだけで安全が長く続くとは限らないためです。
駆除されて空いた縄張りに別のクマが入り、出没が続くことがあります。
加害を繰り返す個体の見きわめも難しく、関係のない無害な個体まで駆除してしまうおそれがあります。
生ゴミや果樹(たとえば柿)放置などクマ出没の原因が残れば、同じ問題が何度も起きる可能性があるのです。
生態系への影響も挙げられます。
クマは森林の生態系において重要な役割を担っており、果実を食べて種を運ぶことで植物の分布に貢献しています。
また、シカやイノシシを捕食することで、クマが森林を食害から守っているとも言えます。
安易に駆除を進めてしまうと、森林全体の環境バランスが崩れる可能性があるのです。
そのため、駆除よりも根本的な原因への対策で「人とクマの棲み分け」が優先されるべきだという考え方が広まっています。
クマの駆除に反対する人の意見

クマの駆除に反対する人々の意見は、主に生命の尊重と環境保護の観点から成り立っています。
反対派の多くは、クマも同じ地球上に生きる生命であり、むやみに命を奪うべきではないと考えているのです。
クマが人里に出てくるのは、本来の生息地が失われたり食べ物が不足したりするためであり、クマ自身に責任はないという考え方が基本になっているようです。
残っている問題を解決せずに駆除だけを進めても、根本的な解決にはならないのです。
こうした反対意見の背景には、人間と野生動物が共に暮らせる社会を実現したいという願いがあります。
現在、九州にはツキノワグマがいませんが、その理由は人間による狩猟・駆除と伐採や集落拡大による生息地の破壊で絶滅したためと言われているのです。
ただし、SNSでは単に「かわいい」という理由で駆除に反対している一部の愛好家も見られます。
実際に被害を受け、クマへの恐怖が残る土地の人たちにとっては、人が安全に暮らせることが重要であるということをもっと理解する必要があると思います。
。
クマ撃退の猟犬『カレリアン・ベア・ドッグ』という選択肢

世の中にはクマ撃退に特化した犬がいます。
カレリアン・ベア・ドッグは、フィンランドのカレリア地方が原産の猟犬で、クマやイノシシなどの大型動物を相手に「吠えて威圧して近づけない」ことを得意とするスピッツ系の犬種です。
適切な訓練と運用で、人とクマの距離を保つ“共存方法”として力を発揮します。
フィンランドを中心とする北欧に加え、米国・カナダ・日本の軽井沢で「野生動物管理の作業犬」として飼われている、国際的なワーキングドッグです。
カレリアン・ベア・ドッグの主な特徴

- 警戒心が強く勇敢で、距離を保って激しく吠え続ける
- 飼い主への忠誠心が高く、指示への反応が速い
- スタミナがあり、寒さや悪路に強い
黒地に白い模様の被毛と、くるりと巻いたしっぽが特徴です。
体高はおおよそ50~60cm、引き締まった筋肉質の体つきをしています。
クマを駆除しない!海外の共存・共生方法は?
海外では、猛獣と人間が棲み分けるためのさまざまな工夫が実践されています。
特に参考になるのは、北米やヨーロッパでのクマやオオカミとの共存事例です。
これらの地域では、長年の経験から効果的な対策が確立されています。
クマを人里から遠ざける取り組み
北米では、電気柵の設置が広く普及しています。
農場や住宅地の周囲に電気柵を張ることで、クマなどの大型動物の侵入を物理的に防ぐことができます。
また、ゴミ箱にはクマが開けられない特殊な構造のものが使用されており、食べ物の匂いで引き寄せられるリスクを減らしています。
アメリカ・ワシントン州では捕らえたクマを山に放つときに犬と銃(ゴム弾)で威嚇して怖い思いをさせ、二度と人里に近づかないようにしています。
ヨーロッパでは、家畜を守るために番犬を配置する伝統的な方法が見直されています。
特にイタリアやスペインでは、オオカミから羊を守るために訓練された大型犬が活躍しています。
さらに、観光客向けの教育プログラムも重視されており、国立公園などでは「野生動物に餌を与えない」「適切な距離を保つ」などのルールを徹底的に周知しています。
共存を念頭に置いた取り組みにより、人間の行動が野生動物の習性に影響を与えないよう配慮されているのです。
海外の成功例から学べることは多く、日本でも応用できる方法はまだあるのではないでしょうか。